学而図書は、なぜ本をつくるのか
学而図書は小さな出版者であり(「社」ですらなく)、代表の私は病気持ちで、積極的な営業もできなければ、表だっての広報活動もできません。そんな有様の人間が出版活動に踏み切ってしまった理由は、先に版元ドットコムで執筆の機会をいただいた「版元日誌」に、隠し立てなく記した通りです。
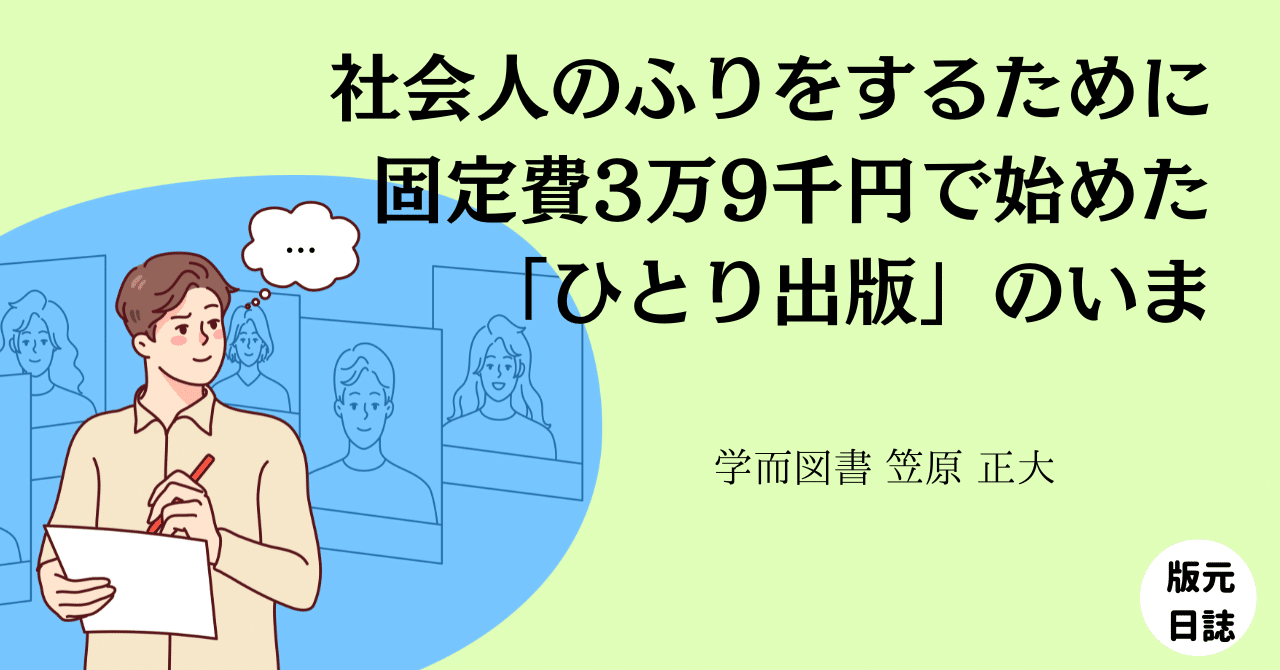
ただ、もともとご縁のあった先生方とのお仕事が中心であるために、学而図書の出版者としての信条や理念について丁寧に述べることを、これまで私は怠ってきてしまいました。ホームページに多少の説明は書いてありますが、公式の説明というものは、どうしても簡潔な文章になってしまうものです。私は短いことばで大事なことを説明するのがとことん苦手な人間なので、公的な文章では、本来なら欠けてはいけない部分を捨象してしまいます。
しかし、私が出版者である以上、たとえ稚拙ではあっても、自分の矜恃はきちんと公に示しておかないといけないはずです。その責任を果たすため、私はこのコラムで、学而図書が本をつくる理由を、そして売れようが売れまいが本を出していくことの意味を述べておきたいと思います※1。
※1 出版業界の事情や、市場の変化、流通方法などについて、本記事では一切触れておりませんのでご注意ください。
出版「事業者」を名乗ってよいものかと自傷的に問う
本というメディアを売ることが難しい時代になったとはいえ、商売として考えた場合、学而図書の販売実績というのは、決して立派なものではありません。先ほどご紹介した記事にも書いていますが、印刷代や流通代こそマイナスにはならないものの、私自身の人件費まではとても賄えない、という状態です。
もちろん、商業出版の世界に加えていただいたからには、できるかぎり本の売り上げで事業を成立させなければ、というささやかな使命感は、私にだってあるのです。商品として価値のある本を世に送り出し、広く流通させ、読者の方から代価をいただくという気持ちを忘れてはいけないと、いつも勝手に肝に銘じています。
しかし、聞いていたこととはいえ、書評に掲載されても、著名なネットメディアで特集まで組んでいただいても、さらには作品が映画の原案になっても、それだけでたちまち本が売れるというわけではありません(このあたり、私の想定よりも現実の数字は厳しいものでした)。事業の規模のわりに情報の露出自体は決して少なくないのですから、この販売成績というのは、もう私という人間の商才の無さを見事に証明しているのではないでしょうか。
現状の学而図書は、出版そのものではまったく成り立たない事業です。私は日々、果たしてこれで「出版事業者」を名乗ってよいのか、と自問自答を繰り返しています。実に、体に悪い生き方です。
出版「事業者」ではなく出版「者」として
日頃からこうして自傷的に苦しんでいる人間ですから、「本は売れなければ意味がない」という考え方にも、いち事業者として強く共鳴する部分があります。だからこそ、この時代に専門書を刊行する無謀や、まともな営業活動もできない弱みを自覚しているくせに、販売数が伸びないと、そのたびに悲しい思いをしてきました。
その一方で、ひとりの「出版者」として本をつくるという行為に向き合ったとき、まったく違う感覚が私の中にあることも、また間違いありません。そして、体裁を気にせず正直に言えば、この出版「者」としての在り方だけが、学而図書が本をつくる理由の根本に関わっています。
学而図書は、2024年9月20日、今後の世界の防災・減災を考える上で最重要の一冊であり、論文中心というハードルの高さからたくさんは売れないであろう『TEN Selected Papers 津波災害を根絶する』を、たくさん売るのに向いていないであろう電子書籍※2で刊行しました。
この、商業的に見ればほとんど無謀ともいえる出版を行ったタイミング以外に、学而図書の出版「者」としての理念、すなわち私が本をつくる理由を記しておく機会はないだろうと考え、いまこうして筆を執っています。
※2 電子書籍だけでは商売にならないという事実については、プチ・レトルさまの版元日誌「電子専業出版社が紙出版を始めた理由」で、販売部数と実際の収入額、電子書籍全体の売上が増えているといわれる中で実は減っている1冊あたりの売上など、すばらしく具体的な例を通して説明されています。
「人間の集合知」を信頼するということ
私は、人間の集合的知性というものを、おそらく自身の根本の部分で信じています。最近は「集合知」というと、インターネットであるとか、AIだとか、多数決であるとか、そういうふうに捉えられがちです。しかし、私が感じる「集合」とは、それとはだいぶ異なります。
数年前、一般販売には厳しいと予想される科学誌『TEN』の公刊に携わったとき、その思いを一部の方に向けてお話ししたことがありました。そのときとお伝えすることの本質は同じですが、少し角度を変え、より詳らかに私の考えを述べておくことにします。

私は、その時代の多数決、あるいは多数派というものを、おそらく、心の奥底ではほとんど信じていません。多数決は、人類の歴史上、数多くの賢者を殺し、あるいは社会から葬り去ってきたシステムです。私たち人間は、ソクラテスであれ、イエス・キリストであれ、ガリレオ・ガリレイであれ、誰かを傷つけたわけでも、殺したわけでもない智者を、多数者側の採決によって社会から抹殺してきました。そのような、ときの多数派、主流派の人々による採決を、私は人間の「集合的知性」だと捉えることができないのです。
しかし最初に述べた通り、私に対する多大の敵意が多衆の間に起っていることが真実であることは確かである。そうしてもし私が滅ぼされるとすれば、私を滅ぼすべきものはこれである。それはメレトスでもアニュトスでもなく、むしろ多衆の誹謗と猜忌とである。それはすでに多くの善人を滅ぼして来た、思うにまた滅ぼして行くであろう。私がその最後だろうというような心配は決して無用である。
プラトン著,久保勉訳『ソクラテスの弁明 クリトン』岩波書店,(十六).
ソクラテスを殺したのは、当時の市民によって開かれた裁判です。許しを請うことなく、誇りをもって裁判に臨んだ人間を参加者たちは許さず、ソクラテスは死刑に処されました。イエス・キリストの死を望んだのも、ローマから派遣された総督・ピラト自身ではなく、イエスの罪状を訴えつづけた多数の民衆であったといわれます。地動説を唱えたガリレオ・ガリレイは、晩年を半ば軟禁された状態で過ごすことになりました。孔子もまた、為政者からその理想を受け入れられないまま流浪の旅を重ね、60歳を過ぎてなお、食料が尽きて飢えに苦しむといった辛酸を嘗めています。
しかし、不思議なことですが、たとえ世間から罵られて死刑に処されようと、記録をすべて焼却されようと、そこに真実が宿ったものは、あらゆる艱難辛苦を乗り越え、人の世で引き継がれてきたのではないでしょうか。もちろん、それを介在するのもまた、個々の人間にほかなりません。ただ、総体として人間の歩みを眺めるなら、それは人類全体の意志が選び取ったかのように、優れた思想が人のうちで残り、継承されていくものと私には見えます。
私がいち出版者として「信じている」と公言する「集合的知性」とは、そういうものです。
個を超えた「集合知」の火にくべる薪をつくる
そのとき説かれているもののうちから、何が残り、何が滅びるのかは、その時代の多数派や権力側にいる人間が決めるのではありません。それを最後に選びとるのは、個の意志を超えた、より大きな流れのようなもの、人間の集合的な知性としか呼べないような何かなのだと、私は独り善がりに信じています。
それは、人間自身がものを探究する熱量に支えられて運動を続け、一時的な多数の意図や権力者による選別を踏み越えて、ひとりの人間の生存期間を大きく超えた時間を費やしながら、容赦なく知を選別していくものです。
まるで回転を続ける巨大な運動体のような、あるいは燃え続ける炎のような、恐ろしく膨大な熱量に支えられて動き続けていく人類の知性の渦の中に、私自身の意志をもって一本の薪を投げこむことが、この学而図書にとっての「出版」にほかなりません。
私が出版者として担うべき仕事は、人間にとって価値があると己が感じた「ことば」を散逸させず、書物として形を整え、流通させ、運動する人類の知性に後を託すという営み、ただそれだけと考えています。学而図書の仕事はそこまでであって、その果てに何が選ばれるのかを知りたいと思うのは、おそらく、私の分際を超えた願いなのでしょう。
出版とは祈りであり、本とはその供物である
このような思いを抱いて出版に携わっている以上、私にとって「出版」とは、そして「本」とは何なのかを問われたなら、誤解を恐れずに次のようにお答えするしかありません。私にとっての出版とは、人間の知性という巨大な運動へと捧げる祈りのような行為であり、本とは、そのために自分の誠心誠意をもって仕立てた供物に類するものなのです。
ちっぽけな出版業者が何を大げさな、と思われることでしょうが、嘘偽り無く自分の心情を述べれば、こうなってしまうのですから仕方がありません。こうした思いは、科学誌『TEN』を学而図書から出版する覚悟を述べた際に触れたところでもありますから、この数年、私はずっと、こういう感覚のもとで本をつくってきたことになります。
――誤解を招かないように付け加えておきますと、たくさんの人に受け入れられることが悪い、と述べているわけではないのです。そもそも、私は出版事業者であって、できるだけ多くの人に読んでもらいたいと思って本をつくっているのですから。ただ、いま人々に受け入れられなかったとしても、それが本の価値のすべてをあらわしているわけではありません。
ところで、私が「人間の集合的な知性」というものを漠然と思い描いたきっかけになった本が、民藝運動の提唱者として著名な、柳宗悦の著書『民藝とは何か』でした。
こういった種類の記事は誰にも読まれないかもしれませんが、次回へと続きます。民藝の思想との出会いが学而図書の出版方針に与えた影響や、社会的生物としての人間の「知」の在り方、そこに向けて「書かれたことば」を投じる意味などを、引き続き述べさせてください。




